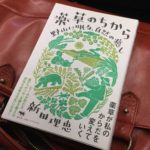「ヒマラヤの薬草と人々の暮らし」聴いてきました

フィールドワークの話を聴くのは、大好きで、
ワクワクする。

Facebookを見ていたら、数日前に「増席しました」というのが、目に入り、
予定を見たら、行けそう‼︎
で、即 申し込み!
- 京都寒い 五条の橋の上やし〜
ヒマーラヤのくらしと、薬草・伝承医療について、京大大学院客員研究生 長岡 慶さんのお話を聞いてきました。
ナビゲーターは、国際薬膳調理師で薬草研究もされている新田 理恵さん。
ヒマラヤ山脈の東山麓、インドのアルナーチャル・プラデーシュ州タワンの暮らしをスライド写真を見せていただきながら聞いた。
ブータンやチベット自治区と接していて国境紛争にさらされてきた地区だ。
大きな「自然」の中で、ゆっくりと生きる
自然と神とも溶け込んだ、壮大な世界観
仏教の教えと伝承が人々の暮らしと縦横の糸のように織り成され、その中に確かな「叡智」が存在している。壮大な物語のように…
大地や自然と、神と、一緒に息をするような暮らし。急かされ、喧騒の中に自分を見失いそうな私たちの暮らしと比べてしまう。
さてさて、
生業は、畑と放牧。
住居と段々畑は3000〜4000mあたりで。
放牧はもっと高い5000mあたりの山の上を移動しながら行っているのだそうだ。
食事(料理)は、ブータンのそれによく似ているとのこと。
穀物は、オオムギ・シコクビエetc
野菜はトウガラシ・キャベツ・ニンジン・ナスなど
乳製品や山菜も
主食は、シコクビエを粉にしてそばがきのようにしたものなど。
餃子やラーメン、ほうとうによく似たものも、あるそうだ。
薬草だけでなく、食を含む生活の様子に興味津々。
生活の中に、「香」(香木)の習慣がある。
シャクナゲ(ツツジ科)の葉や ビャクシン(ヒノキ科)の葉、
ヒマラヤモミ(マツ科)の葉
これらのいずれかを、毎朝清めのために焚くのだそうだ
チベット医療では、薬草を主とした「丸薬」処方が中心だが、
「この症状には、この薬」というわけではなく、
この人のこの状態には、この薬を、といった一人ひとりに合わせるし、
朝昼晩で処方が違うのだそうだ。
飲む期間も短くても3か月ぐらい身体の本来のバランスまで整える感じだ。
一つの丸薬に多くの種類の薬草が含まれていて、その丸薬が150種類くらいあって、それらを組み合わせて処方(朝昼晩違うし)
それらを操る 医師って凄いわーって感嘆する。
最後は、
どこの家でも毎日、何杯も飲まれるという「バター茶」の実習
- 混ぜます
- 左端が長岡さん
- バター茶 出来上がり
やっぱり現地のとは違うみたいですが、
foodはそこの風土があるからこそですから。
ほんとの最後に、新田理恵さんの著書の紹介があって、
「北から南、四年かけて」と聞いて、これは買わなくっちゃ(フィールドワークと聞くと惹かれる)
- 身近な薬草がいろいろ
- 前田さんと。笑顔が素敵な方です
オレンジブロッサム最新予約状況
| トリートメント、教室、カウンセリング予約可能 | |
| 教室、カウンセリング予約可能 | |
| 教室開催日 |

このブログの著者
メルマガ登録
毎月一つ、香水教室に通って香水を作ること約9年。
そこで得たり感じたりした香りや香水についてのいろいろを、少しづつお伝えします。
お伝えする内容は
(1)香水の扱い方、歴史などミニ知識
(2)季節の香り
(3)プレゼントした香水のミニ解説
月2回ほど、毎回、(1)と (2)or(3)について綴ってまいります。